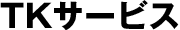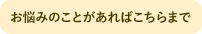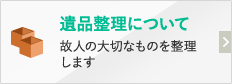大阪の実家が“開かずの間”になってませんか?骨董品が眠る家のリアル
目次
大阪の実家で増える“開かずの間”とは?
大阪で片付けのお手伝いをしていると、よく出会うのが「開かずの間」です。 長年手を付けていない部屋や押し入れは、気づけば荷物で埋まり、誰も近づかない空間になってしまいます。 特にご高齢の方が住む家では「とりあえず置いておく」という習慣が積み重なり、物があふれていくのです。
大阪特有の「もったいない文化」と片付け
大阪は「商人の町」としての歴史を持ち、「まだ使えるから置いておこう」「いつか役立つかもしれない」と考える方が多い地域です。 この“もったいない文化”は素晴らしい一方で、片付けを難しくする原因にもなっています。 特に昭和の時代に買った家具や家電、食器類は「丈夫で捨てにくい」ため、今もそのまま残っているケースが目立ちます。
開かずの間に眠る“お宝”の可能性
私たちが現場で片付けをお手伝いする際、「これは処分かな?」と思っていたものが、実は価値ある骨董品だったというケースは少なくありません。 たとえば:
- 古い掛け軸や屏風
- 昭和のキャラクター玩具
- アンティークの食器やガラス製品
- 戦前の絵葉書や切手
大阪の古い家ほど、こうした“眠れるお宝”に出会える可能性が高いのです。
開かずの間を片付けるためのステップ
開かずの間を片付けるには、次のようなステップが効果的です。
- まずは部屋の中身を把握する(仕分けの第一歩)
- 「処分するもの」「残すもの」「価値がありそうなもの」に分類する
- 骨董品や昭和レトロ品は専門家に査定を依頼する
- 残すものも収納を工夫して“再び物置化”しないようにする
一人で片付けようとすると途中で心が折れてしまうことも多いため、プロに相談するのも有効な方法です。
まとめ
大阪の実家に増えている“開かずの間”問題は、決して珍しいことではありません。 背景には大阪特有の「もったいない文化」があり、その中には骨董品や昭和レトロ品といった思わぬ価値ある品が眠っている可能性もあります。 放置してしまう前に、一度片付けに向き合うことが大切です。